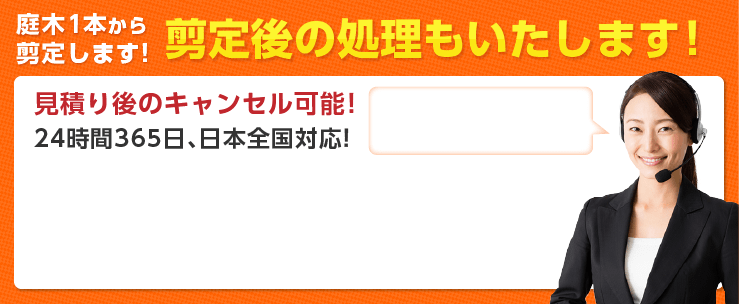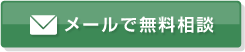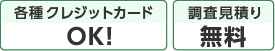植木剪定を効率的にするには時期がポイント!費用を抑える方法も解説

植木のお手入れのひとつである剪定は、年に1~2回おこなうのが一般的です。剪定は手間のかかる作業のため、つい後回しになることもあるかもしれません。しかし、植木剪定はきれいな樹形を保つだけでなく、木の健康を維持するためにも重要なお手入れです。放っておくと木が弱って枯れてしまうこともありますので、定期的におこないましょう。
とはいえ、「剪定の作業は疲れるし時間がかかる」、「業者に依頼すると費用がかかってもったいない」という理由で、剪定をおっくうに感じている人もいるでしょう。ただし、剪定は適切なタイミングでおこなえば、無駄に何度も作業をしなくても済み、労力や費用を抑えることができます。
このコラムでは、剪定のベストな頻度やタイミングについて解説します。費用を抑えるために自分で剪定する方法や業者選びのコツもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
植木剪定は年1~2回!適した時期におこなおう
生垣などのとくに見栄えを重視する木の場合は、年に3回以上剪定をすることもありますが、最低限必要な剪定の頻度は年に1~2回と考えてよいでしょう。まずは、植木剪定をするのに最適な時期を解説します。
強剪定と弱剪定を1回ずつが基本

剪定の頻度は、木の成長速度によって変わってきます。成長が遅い木は年に1回の剪定で済むこともありますが、成長の早い木は年に2回程度剪定をするのがよいでしょう。
剪定には、大きな枝をつけ根から切り落とす強剪定と、伸びすぎた枝を整えたり不要な枝を取り除いたりする弱剪定があります。強剪定は木の形や大きさを調整する骨格作りの剪定、弱剪定は木の見栄えや健康を保つお手入れの剪定といったイメージです。
成長の遅い木は枝があまり伸びないので、基本の樹形が乱れることはそれほどありません。そのため大きな剪定は必要なく、お手入れである弱剪定を年に1回だけおこなうことが多いです。数年に1度、強剪定をして大きさを調整することもあります。
成長の早い木は強剪定と弱剪定をそれぞれ年に1回ずつおこなうのが基本です。強剪定では枝を大きく切って基本の形を作ります。成長の早い木はすぐに枝が伸びてしまいますので、強剪定の後に伸びた分の枝を弱剪定で整えるのです。
剪定に適した時期とタイミング
大きな枝を切るほど、木にとってはダメージが大きくなります。そのため、剪定はダメージに耐えられるだけの体力が木にある時期を見計らっておこなう必要があるのです。
また、木の成長が活発な時期に剪定をしてもすぐに枝が伸びて、またすぐに剪定をしなければならないこともあります。剪定の適切な時期を知っておくことで効率をよくし、剪定作業の回数を減らすこともできるのです。
適切な剪定の時期は、木の種類によって違います。それぞれの時期の目安は、以下のようになっています。

木に十分な体力がある時期には強剪定を、ある程度体力がある時期には弱剪定をすることができます。年に2回剪定をする場合は、強剪定の時期と弱剪定の時期にそれぞれ1回ずつおこないましょう。年に1回の場合、強剪定の時期に弱剪定をおこなうことは可能です。ただし、強剪定は必ず目安の時期におこないましょう。
7月~8月ごろの真夏は多くの木にとって成長期です。この時期に剪定をすると木は切られた枝を元に戻そうとかえって枝を伸ばし、樹形を乱してしまいます。また、多くの針葉樹は寒さに強いので冬でも弱剪定は可能ですが、春に新芽を出すのでそのころにまた剪定が必要です。
常緑樹や針葉樹の強剪定は、成長期直前の3月~6月ごろにまとめておこなうのが効率的です。その後、夏の間に伸びた枝を9月~11月ごろに弱剪定で整えるというのが最適な方法でしょう。
落葉樹は、休眠期である11月~2月ごろに強剪定ができます。冬の早い時期に強剪定をした場合には春ごろ、遅い時期にした場合は秋ごろに弱剪定をするようにすると効率がよいでしょう。
剪定の費用を可能な限り抑える方法
植木剪定を業者に依頼した場合には、費用がかかります。しかし、費用はできるだけ安く抑えたいという人が多いでしょう。そこで、剪定にかかる費用の相場と、費用を抑える方法をご紹介します。
剪定業者の費用相場
剪定業者の料金設定には単価制と時間制があり、木の大きさや本数、作業時間などによって変わります。また剪定の作業費とは別に、切った木の枝を処分する費用も発生することもありますので、事前に見積りを取って確認しましょう。それぞれの相場は以下のとおりです。

たとえば高さ4mの木1本の剪定を依頼し、ゴミも引き取ってもらった場合、単価制なら17,000円程度がかかります。4mの木の剪定にかかる時間は作業員がひとりならおよそ5時間が標準的ですので、時間制なら23,000円程度という計算になります。決して安くはない金額ですが、年に1~2回で済ませることができれば出費を抑えることができます。
「費用がかかるから剪定しない」は危険
なんとか剪定の費用を抑えたいところですが、そのために決してやってはいけないのは、剪定をしないでおくということです。剪定は木にとって重要なお手入れですので、しないで放置することには多くのリスクがあります。木の剪定をしていないとどんなことが起きるのか、みてみましょう。
・事故やトラブルの原因になる
木の枝が伸びすぎて道路にはみ出していたり、上に伸びた枝が電線や電話線に接触していたりする場合は、事故の原因になるおそれがあります。また、枝が隣家の敷地内に侵入している場合には、落ち葉で隣家の庭を汚すなど、トラブルの原因にもなるのです。
事故やトラブルを避けるために、支障がありそうな枝は早めに剪定で取り除いておくことが必要です。
・木が枯れたり病気になったりする
枝葉が多すぎると木の内側は陰になって日が差し込まなくなり、内側の枝は十分な光合成ができず、弱ってしまいます。また、枝が混みあっていると風通しも悪くなり、木の内側に湿気がこもって病原菌や害虫が発生しやすくなるのです。剪定には、枝の量を適度に減らすことで日当たりと風通しを確保し、木の健康を維持する役割もあります。
・成長が悪くなる
木には、ほかの枝よりも優先的に栄養を使ってしまう枝がときどき生えてきます。このような枝を放っておくとその枝ばかりが成長し、木全体の成長が悪くなるのです。剪定で枝を切ることは、成長させたい部分にうまく栄養を誘導するテクニックでもあります。
・樹形が乱れる
木の枝は放っておけば、各々が自由な方向に伸びていきます。自然ときれいな樹形になる木もありますが、多くの木は剪定をしなければ全体のバランスが崩れ、見栄えが悪くなるのです。定期的な剪定でバランスを整えることで、美しい木の形を保つことができます。
費用を抑える方法
剪定は必要なお手入れですが、やはりできるだけ費用は抑えたいところでしょう。そこで、費用を安く抑えるための方法をいくつかご紹介します。
・適切なタイミングで依頼する
木には最適な剪定の時期がありますが、剪定の業者は依頼をすればいつでも剪定をしてくれることが多いです。しかし、適切でない時期に剪定をおこなうとすぐに枝が伸び、効率的でないこともあります。適切なタイミングで業者に依頼をすることで剪定をする回数を減らし、年間を通した剪定の費用を減らすことが可能です。
・業者を吟味する
料金の設定は、業者によって違いがあります。同じサービスでも、より安い料金を設定している業者はあるかもしれません。それぞれの業者の料金設定や内訳をよく確認し、相見積りを取って比較するなどして、業者を吟味しましょう。業者の選び方については、この後の「費用を抑えるための業者選びのコツ」でくわしく解説しています。
・ゴミの処分を自分でする
業者によっては、剪定で出たゴミの処分に追加費用がかかる場合があります。その場合、ゴミの処分のみ自分でするようにすれば、その分の費用を抑えられるのです。また、ゴミ袋を自分で用意すると費用が割引になる業者もあります。ゴミの処分方法については、この後の「自分で剪定する場合の注意点と業者のメリット」の「ゴミの処分」をご覧ください。
・剪定を自分でする
そもそも、業者に頼まないというのも究極の節約です。植木剪定は木のお手入れのメインといってもよい作業ですので、自分でできるようになればいっそう植木を育てるのが楽しくなることでしょう。自分で剪定をする方法については、この次の項目で解説します。
自分で剪定して費用を節約する方法
植木剪定を自分ですることができれば、費用を大幅に節約することが可能です。ここでは、自分で剪定をする方法をくわしく解説していきます。
剪定に必要な道具

剪定には、剪定用の道具が必要です。木の大きさや枝の太さ、剪定の方法によって使う道具は変わってきますので、必要に応じてそろえておきましょう。
・植木バサミ
細い枝を切るハサミです。
・剪定バサミ
やや太めの枝を切る、ニッパーのような形をしたハサミです。
・高枝剪定バサミ
長い柄がついていて、手で届かない高い位置の枝を切ることができます。
・剪定ノコギリ
ハサミで切れない太い枝を切るのに使います。
・刈り込みバサミ
木の表面を切りそろえるのに使う、刃と持ち手が長く、両手で使うハサミです。
・ヘッジトリマー
刃が自動で動き、楽に刈り込みができる道具です。
・脚立
高い位置で作業をするのに使います。バランスのよい3脚のものがおすすめです。
・手袋
木のトゲや害虫などから手を守るために、革製の手袋やラバー軍手などを着用しましょう。
・癒合剤
枝を切った切り口を保護するのに使います。
基本の剪定方法は3種類
剪定の方法にはいくつか種類がありますが、自分で剪定をする場合には以下の3種類を押さえておけば十分でしょう。それぞれ簡単に解説します。
・間引き剪定
その枝自体が不要だという場合に、根元から丸ごと切り落としてしまう方法です。枝の数を減らすことで、日当たりと風通しをよくする効果があります。太い枝を何本も切り落とす場合は木の負担が大きくなりますので、強剪定の時期におこないましょう。
・切り戻し剪定
長い枝を、途中で切って短くする方法です。木の大きさを小さくまとめたり、枝の伸び方を調節したりして樹形を整えます。木への負担は少ない方法ですが、量が多い場合には弱ってしまうこともありますので、時期によって切り方を加減しましょう。
・刈り込み剪定
木の表面の枝葉を切りそろえて、形を整える方法です。生垣などの見栄えをよくします。先端の枝葉を切るだけなので木の負担が少なく、頻繁におこなうことができる方法です。ただし、時期と程度によっては弱ったり、花が咲かなくなったりすることもあるので注意が必要です。
切る枝を見分ける4つのポイント
剪定でもっとも重要なのは、どの枝を切ればよいのかをみきわめることです。やたらに切っていると木が弱ったり、枝の伸び方がかたよって樹形が乱れたりします。切るべき枝をみきわめるポイントは、以下の4つです。
・病気の枝や枯れた枝
病原菌や害虫に侵されている枝やすでに枯れてしまった枝は、放っておくとほかの枝や幹も巻き添えにしてしまいます。早めに取り除きましょう。
・混みあう枝
ほかの枝と交差する枝や内側に伸びる枝、幹の途中から生えている細い枝などの内側で混みあう枝は、日当たりや風通しが悪くなる原因です。不要な枝ですので、根元から切り落とします。
・栄養を独占する枝
ほかの枝と比べて極端に成長の早い枝や株元から生える新しい枝は、栄養を独占してほかの枝の成長を妨げます。元気な枝なのでもったいない気もしますが、思いきって切ることが大事です。
・樹形を乱す枝
下向きや真上に向かって伸びる枝、同じ位置から複数生えている枝は、樹形のバランスを崩します。その枝が伸び続けたら樹形がどうなるかをイメージして、切るかどうかを判断していきましょう。
剪定が上手にできる6つのコツ
どの枝を切ればよいのかがわかったら、今度は枝を切るときのコツをみていきましょう。枝を切るときには、切る位置に注意する必要があります。
・切り残しがないように切る
枝をすべて切り落とす場合には、切り残しがないように枝のつけ根で切りましょう。切り残した部分には十分な栄養が送られず、切り口がふさがりにくくなります。その切り口に病原菌などが入り込み、枯れてしまう原因になるのです。
・太い枝は強剪定の時期に切る
太い枝を根元から切り落とすと切り口が大きく残り、葉の量も大幅に減るので、木の負担が大きくなってしまいます。太い枝は、木に体力のある強剪定の時期に切ることが望ましいです。ただし、枯れた枝や支障のある枝の場合はやむをえないこともあります。切り口に癒合剤を塗るなどして、その後のケアに注意しましょう。
・太い枝は3ステップで切る
太い枝をノコギリで一気に切り落とそうとすると枝の重みで切り口が裂け、幹の部分にまで傷が残ってしまうことがあります。太い枝は、まず根元の少し先に下から切り込みを入れ、またその少し先で上から切っていきます。下に切り込みを入れておくことで、枝が裂けたとしても切り込みのところで止まるのです。その後、改めて根元部分を切り落としましょう。
・枝の節目で切る
枝を途中で切るときは、葉や芽のすぐ上で切るのがポイントです。中途半端な位置で切ると、先端部分が枯れてしまうことがあります。また、残ったほかの枝がバランス悪く伸びてしまうこともあるのです。
・外芽を残して切る
新しい枝の芽には内側に向かってついている内芽と、外側に向かう外芽があります。枝を途中で切る場合には先端に外芽が残るように、外芽のすぐ上で切りましょう。そうすることで新しい枝が外側に伸び、樹形のバランスがよくなります。
・Yの字に残して切る
枝の長さを短くしたい場合には、1番先端にある枝を切りましょう。先端の枝を枝分かれのつけ根部分で切り、残った枝がYの字の形になるようにするのがポイントです。そうするとその枝はそれ以上縦方向へは伸びず、残った枝が横に広がって伸びるようになります。
自分で剪定する場合の注意点と業者のメリット
自分で剪定をすれば業者に依頼する費用はかかりませんが、いくつか注意点もありますので、確認しておきましょう。自分で剪定をおこなう場合と比較した、業者のメリットについてもご紹介します。
ゴミの処分

剪定で出たゴミの量が少量であれば、通常の可燃ゴミと同じようにゴミ収集に出すこともできます。ただし枝をゴミとして出す際には、自治体によって枝の太さや長さ、一度に出せるゴミ袋の数などに制限がある場合もありますので、自治体の情報を確認しましょう。
量が多い場合にはゴミ処理場に自分で持ち込むか、不用品回収の業者に依頼するといった方法もあります。ただし、この方法は費用がかかります。また、自宅などで焼却処分することは法律で禁止されていますので、しないようにしましょう。
植木剪定の業者では、剪定した後のゴミを処分してもらうことも可能です。別途費用がかかることもありますが、ゴミの量が多い場合や、自分で処分するのと費用が変わらないような場合には利用してみてもよいでしょう。
木が弱るリスク
剪定は木にとって負担であり、本来は知識と技術が必要な難しい作業です。木の状態をみて切る枝や程度を判断し、木の健康と見栄えを両立させなければなりません。もしも剪定に失敗すれば、木が弱って枯れてしまうおそれもあります。枯れてしまうと回復するのは難しくなりますので、自分で剪定をすることには大きなリスクがあるともいえるのです。
多くの木を剪定した経験のある剪定業者は、どの枝を切れば木にどれくらいの負担がかかり、どんな状態になるかといった知識をもっています。そのような業者に任せれば、木が枯れてしまうリスクを回避することができるでしょう。
時間と労力
剪定の作業には当然ながら、時間と労力がかかってしまいます。慣れない人であればなおさら、丸1日がかりになってへとへとになってしまうこともあるでしょう。剪定業者に任せれば、せっかくの休日をつぶして疲労をため込むことはありません。
業者は作業時間が早く、仕上がりも自分でするよりもきれいにしてくれるでしょう。業者によっては作業中の立ち会いが必要ないこともありますので、出かけている間に木をきれいにしてもらうということも可能です。
費用を抑えるための業者選びのコツ
植木剪定を業者に依頼するとすれば、よい業者を選ぶことが重要です。満足のいくサービスをしてくれることはもちろん、できるだけ費用が安い業者をみつけたいところでしょう。費用を抑えるための、よい業者のチェックポイントを解説します。
出張費の有無

業者によっては、現場まで移動するための出張費が料金に別途加算されることがあります。出張費がかかるかどうか、業者のサイトなどを調べて確認しておきましょう。出張費無料の地域を設定している業者もありますので、できるだけ近場の業者を探すのもポイントです。
見積り料やキャンセル料の有無
見積りを取るだけで見積り料が発生したり、見積りをみてから断るとキャンセル料が発生したりといった業者もあります。見積り料やキャンセル料がかからない業者であれば、まだ頼むかどうかわからない段階でも気軽に相談ができるでしょう。また、こういった費用がない業者は、それだけサービスに自信がある証拠だともいえます。
詳細な見積り
見積りに詳細な内訳が書かれていて、それがどのような費用なのかを説明してくれる業者が信頼できるでしょう。なににどれだけの費用がかかっているのかはっきりしていれば、後から追加費用がかかることも少なくなります。見積りの段階でていねいに説明してくれれば、「このサービスはいらないからその分安くして」といった交渉もできるかもしれません。
相見積りを取る
相見積りは、複数の業者から見積りを取ることです。いくつかの業者の費用やサービス内容を比較することで、よりよい業者を選ぶことができます。最低でも3社程度は見積りを取るのがよいでしょう。相見積りをするためにも、見積り料がかからない業者を選ぶことも大切です。
業者探しなら弊社にご相談ください!
剪定業者は限りなくありますので、選ぶだけでも大変な作業になってしまうでしょう。業者選びに迷ってしまうという場合には、ぜひ弊社にご相談ください。弊社では、全国の加盟業者のなかからご相談内容に応じた業者を無料でご紹介するサービスをおこなっています。
弊社の剪定は1本1,000円~と、一般的な相場に比べて安い料金で提供することが可能です。見積りは無料ですし、キャンセル料や追加費用なども一切発生しません。費用のほか、剪定方法やゴミの処理など、サービス内容のご要望があればお気軽にご相談ください。
数多くの加盟業者のなかから厳選しますので、ご要望に対応できる業者がきっとみつかります。弊社では、24時間年中無休の電話相談を受けつけています。植木や剪定、業者探しで困ったときにはいつでもお気軽にお電話ください。
剪定の関連記事
- ヤツデの剪定と育て方|大きな葉と白い花が特徴!縁起物の人気植物
- 大王松(ダイオウショウ)の剪定方法|剪定道具や注意点・育て方も
- 庭木の剪定をプロにまかせる!プロ集団があなたの庭をお助けします!
- 藤の剪定方法と花が咲かない原因|棚でも盆栽でも楽しみたい方へ
- オリーブの剪定にチャレンジ!オリーブの剪定方法やコツを理解しよう
- キウイの剪定方法と時期|枝の絡まりを防いで美味しい実を育てよう!
- モッコクの剪定方法を解説!時期・切り落とす枝の見極めが重要
- 柿の木を剪定方法を解説!タイミングと方法・収穫のための作業も
- シラカシ剪定|スッキリさせて庭のシンボルツリーに!時期・方法紹介
- ネズミモチの剪定時期や方法を解説!初心者でも簡単に育てられます