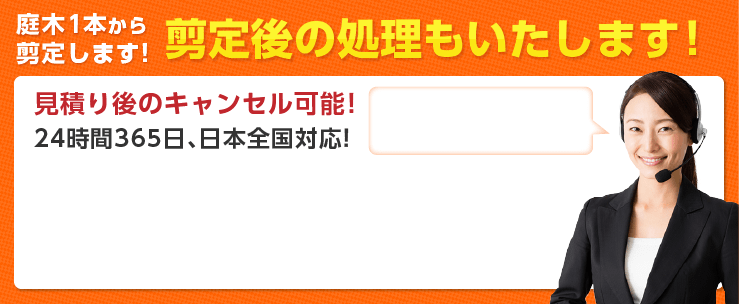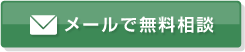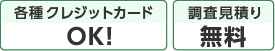柿の木を剪定方法を解説!タイミングと方法・収穫のための作業も

柿は庭でも育てることができる、人気の木です。しかし、柿の木をはじめとした庭木のお手入れ方法はあまり広く知られておらず、調べてもよくわからないという人も多いのです。
柿の木は、剪定をはじめとしたお手入れがとても重要です。お手入れ次第で、きれいに実がなるか枯れてしまうかが変わってきます。
今回は正しい柿の木の剪定方法や、おいしい実がなる方法をお教えします。柿の木を育てているけど、お手入れ方法がわからない方は必見です。
目次
柿の木の剪定を自分でやるために知っておきたい知識
柿の木の剪定する前に、剪定についての知識を身につけましょう。なぜ柿の木を剪定しなくてはいけないのか、いつ剪定すればいいのかを知ることで、実際の剪定をより正確に美しくおこなうことができます。
なぜ柿の木を剪定するのか?

柿の木を剪定する理由は、以下の三つが挙げられます。
・おいしい実をつけるようになる
木に柿がなりすぎると、実に届く栄養が分散されてしまうのです。そうなると、実ひとつに生き渡る栄養が少なくなってしまい、おいしい実がつけられません。剪定で実の量を調整することによって、実に生き渡る栄養が増えるのです。
・木の管理を楽にする
樹形を整え適度な大きさにすることで、実の収穫や農薬の散布が楽になったりすることがあります。また木が大きすぎると、病気にかかったり虫に食われていたりする葉や枝を探すのに、苦労がいるのです。
・病害虫を防ぐ
枝や葉の密度が高くなると、日当たりや風通しが悪くなってしまいます。そうなると日光に弱い害虫や、カビなどの病原菌がすみつきやすくなります。剪定して枝や葉の密度を少なくすることで、日当たりや風通しがよくなり、病害虫の予防につながるのです。
正しい剪定時期は?
柿の正しい剪定時期は、11~2月の冬です。この時期は休眠期といって、木の生長が止まるタイミングなので、剪定しても木の生育に悪影響を及ぼしません。もし11~2月以外で枝や葉が密集して剪定したいという場合は、6~7月に軽く剪定しましょう。
正しくない時期に本格的な剪定をしてしまうと、実がつかなくなったり木が弱ってしまったりするので気をつけましょう。
どのように切ればいいの?
剪定のポイントとしては、以下の三つが挙げられます。これらを意識して剪定をするとよいでしょう。
・横に広がるように剪定する
柿の木は普通の木と違い、横に平べったい形になるように剪定した方がよいのです。理由としてはふたつあります。
ひとつは横に広がるように剪定することで、幹に日が当たりやすくなり実のつき方がよくなるのです。もうひとつは、横に伸ばすことで高所での作業がなくなり、お手入れが楽になるからです。
・その年に実がついた枝を切る
柿は、前の年に伸びた枝の先に実をつけ、その年に実がついた枝は翌年実をつけません。その点を考慮せずに剪定をしてしまうと、全く実が収穫できなくなるおそれがあるのです。実のつかない枝を切り、実のつく枝に養分がいくようにしましょう。
・枝は正しい位置を、垂直に切ろう
枝を切る正しい位置は、新しく枝が芽吹いている部分のすぐ上です。切るさいは垂直に切りましょう。斜めに切ると、他の枝を傷つけるおそれがあります。
剪定方法は若木と成木によって分かれる
柿の木の剪定は、苗を植えてから木が成長しきるまでの若木と、成熟した成木によっても剪定の仕方が変わるのです。その違いについてまとめたので、参考にしてみてください。
・若木の剪定の仕方
若木の時期の中でも、苗を植えてからさほど年数がたっていない「幼木」の時期は、木を生長させることを優先させなければなりません。そのため、剪定で枝を切りすぎないようにしましょう。
幼木の段階が終わって剪定ができる時期になったら、丁寧に剪定してください。ここでポイントとなるのが「主枝」と呼ばれる枝です。
主幹から枝分かれをした枝を主枝といい、主枝が主幹から45度の方向に生えると理想の樹形になると言われています。45度の方向に生えている主枝は残し、それより小さい角度の主枝は剪定しておきましょう。
主枝を剪定するさいは、成木になったさいの剪定作業を楽にするため、30~50cmほどの間隔をあけて切り落としてください。
・成木の剪定の仕方
成木になったら、剪定作業は毎年おこないましょう。剪定作業を怠ると、枝が太くなって切るのが大変になったり、枝分かれが進んで作業量が年々増えてしまったりするおそれがあります。
このとき、積極的に切る枝は古い枝と下に垂れた枝です。柿は、一度実をつけた枝にもう一度実をつけることはありません。ですので、実がついた重さで垂れ下がった枝に実をつけることはないので、切っておきましょう。
剪定のやり方に自信がないときはどうする?
上記を読んで、若木と成木の違いや切り方がわからないと思ったら、業者に相談することをおすすめします。業者は柿の木の剪定時期や方法を熟知しており、それに合わせた剪定をしてくれます。
柿の実りをよくするためにしておきたい作業
柿の木は剪定以外にも、実つきをよくするためにやっておくべきお手入れがあるのです。この項目では、そんな剪定以外のお手入れをご紹介します。
摘蕾・摘果

摘蕾とは余分なつぼみを取り除く作業のことで、摘果は果実を取り除く作業のことです。この作業は、つぼみや果実が多いときにおこなう作業です。取り除くことで、残したつぼみや果実に対して、たくさんの栄養を行き渡ることが可能です。
摘蕾は4~5月にかけておこない、摘果は6~8月にかけておこないます。つぼみは枝の先端に4つほど残し、実はひとつの枝に1~2個ほどあるのが理想です。
ただし摘果は、実がなった直後におこなってはいけません。柿は自分で実の調整をおこなうことができます。しかし、調整前に摘果をおこなうと、実が少なくなりすぎてしまうおそれがあるのです。
水やり・肥料やり
柿は乾燥に弱いため、水切れしないように気をつけましょう。鉢植えで育てている場合は、表面の土が乾いたらたっぷりと水をあげます。特に夏場は、朝夕と1日に2回ほど水やりをするとよいでしょう。
地植えで育てている場合は、植え付け後や日照りが続くときには水やりが必要ですが、基本的に雨のみで育ちます。
柿の木の肥料については、年に2~3回与えましょう。12~1月には寒さに耐えるために、長い効果のある有機肥料を与えてください。実の収穫後には、消耗した体力を回復させるための栄養補給として、速効性のある化成肥料を与えましょう。
また樹勢が弱い場合も、6~7月頃に速効性のある肥料を与えてください。このとき栄養分が多すぎると、枝葉ばかり伸びてしまいますので、適度な量を心掛けましょう。
病害虫の対策
柿の木に起きやすい病害虫は、以下のとおりです。
・丸星落葉病
この病気にかかると、中央部が褐色の丸い斑点が葉にできて、落葉が激しくなります。落葉が感染源なので、落ちた葉は集めて焼却しましょう。発病してからの治療は難しいので、5~6月に薬剤を塗布して予防をしましょう。
・角斑落葉病
その名のとおり、葉に角ばった斑点ができる病気です。こちらも激しく落葉します。丸星落葉病と同じく、5~6月に薬剤を塗布することで対策ができます。
・カキノヘタムシガ
果実の中身へ食い入り、へただけを枝に残して実を地面に落としてしまう害虫です。幼虫は薄茶のような色をしており、体長は4~15mmほどです。対策としては、9月ごろに幹や枝に薬剤を塗布してください。
・イラガ
多くのとげを持つ虫です。葉の裏に寄生をして、葉をかじってしまいます。触ってとげに触れると痛みを感じるので、直接触れないようにしましょう。対策としては、冬に枝についてる繭を集めて焼却したり、幼虫が食い入る前に薬剤を塗布したりしましょう。
また園芸での対策に使われる薬剤には、MEP(フェニトロチオンと呼ばれる有機リン・有機硫黄系殺虫剤)が入ったものが有名ですが、果物である柿の木に殺虫剤を使うのは不安だという方もいらっしゃることでしょう。
しかし、薬剤のなかには食酢100%の商品もあるため、種類を選べば、安全に使用することが可能です。
自分でのお手入れが難しいと感じたら
柿の木を育てているからには、上手に柿の実を育てて味わいたいとお考えの方も多くいらっしゃることでしょう。しかし、柿の実が健康的に育つためには、柿の木を正しく育てながら、病害虫から守ってあげる必要があります。
剪定や消毒など、正しいお手入れをすると木が健康になり、病害虫に対しての抵抗力が高まります。「正しいやり方がわからない」「自分ひとりでできるか不安」という方は、剪定お助け隊へお気軽にご相談ください。
庭木のお手入れは大変……業者をかしこく利用しよう!
剪定だけでも大変なのに摘蕾や摘花、水やりや肥料やりなど、木のお手入れは大変ですよね。そんなときは、業者に相談してみてはいかがでしょうか?この項目では、業者を選ぶポイントや業者に任せられることをまとめてみました。
業者から受けられるサービス

業者によって受けられるサービスはさまざまですが、柿の木以外にもさまざまな木の剪定をおこなってくれたり、不要になった木の伐採や伐根も受け入れてくれたりする業者もあります。
また剪定後のアフターケアとして、癒合剤や消毒のサービスをおこなったり、活力剤を使用したりしてくれる業者もあるのです。上記のサービスを定期的におこなってくれる業者もあります。
料金形態はどうなっているのか?
こちらも業者によって異なります。基本的には、作業費・処分費・出張費などが足し合わされて料金が決定します、しかし処分費と出張費が料金に含まれているものもあれば、含まれていないものもあるのです。詳しい料金形態を知りたい場合は、事前に見積りを取ってもらいましょう。
また複数の業者から見積りを取ることで、平均的な金額がわかるため、適正な価格がどのくらいなのかを自分で判断しやすくなります。本来どのようなサービスにどれだけの料金がかかるのかがわかると、高額請求の業者をふるいにかけることができ、安心して依頼できる業者を見つけやすくなるのです。
業者選びのポイント
業者選びのポイントは、サービスをきっちりとおこなってくれるかどうかを見極めることです。正しく丁寧な剪定をしてくれるか、納得できる費用で作業してくれるか(契約後に追加料金が発生しないか)、質問に親身に対応してくれるかなど、誠実な業者かどうか確認してみましょう。
実績がホームページなどに載っているかを確認するのも大切です。主観が含まれていますが、口コミサイトの感想を確認するのも手です。
弊社では、24時間365日対応のコールセンターが、お客様からのご相談・ご依頼を受け付けております。剪定のご不明点や予算のご相談まで、どんなことでもお問い合わせください。離島を除いた全国で対応しているので、お気軽にご相談ください。
剪定の関連記事
- ジューンベリーの剪定は冬に!剪定のコツ・業者の依頼費相場も紹介
- イロハモミジの剪定|初心者でも失敗しないテク&植え方育て方まとめ
- 花桃の木|剪定の失敗で花が咲かない?正しい方法や基本の育て方解説
- 松の剪定|難しいけど自分で挑戦!枝や葉のどこを切ればいい?
- 観葉植物の剪定方法を解説!知っておきたいポイント・剪定後のケア
- 【刈り込みと剪定】2つの違いは?刈り込みの基本をマスターしよう!
- 金のなる木を剪定して美しく育てよう!剪定時期や方法をご紹介します
- 庭木の剪定をプロにまかせる!プロ集団があなたの庭をお助けします!
- ユズリハの剪定方法|剪定時期や注意点、育て方までまるっと紹介
- 夏みかんの剪定時期・方法を解説!おいしいみかんを収穫するコツも