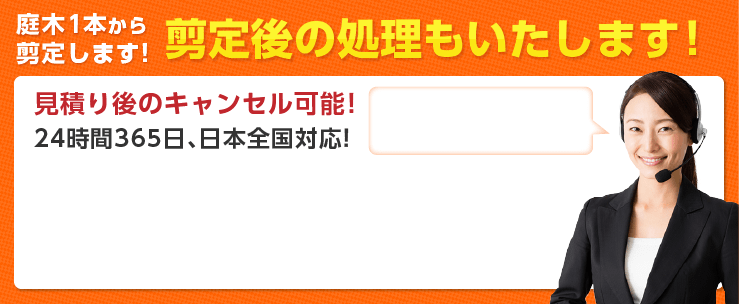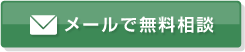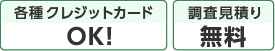アオダモの剪定は自然樹形を活かそう!手入れが簡単なのが人気の理由

マイホームを建てた際などに、家の象徴としてシンボルツリーを植えようと考える人は多いでしょう。しかし、しっかりと育てていけるかどうか不安だという人もいるかもしれません。
そんな人におすすめなのは、アオダモという樹木です。アオダモは剪定などの手入れがあまり必要なく、育てやすい樹木なのです。このコラムではアオダモの特徴と育て方、お手入れの方法について解説します。シンボルツリーをなににしようか悩んでいる人や、これからアオダモを育ててみようと考えている人はぜひ参考にしてみてください。
目次
アオダモに剪定は必要?
アオダモは丈夫で成長が穏やかなので、比較的管理の手間がかからない樹木です。そのため、とくに植木の初心者にはおすすめなのです。アオダモがどんな樹木なのか、その特徴をみていきましょう。
自然樹形を楽しむアオダモ

多くのアオダモは株立ち性です。株立ちとは1本の太い幹ではなく、根元から細い幹が数本伸びてくる樹木のことをいいます。それぞれの幹が細いため、枝葉が伸びてもあまりスペースを取らず、自然樹形で楽しむことができるのです。
枝葉が密生する樹木は自然のまま成長すると木の内側に日が当たらずに枯れこんでしまうことがあります。また、成長の早い樹木は放っておくと大きくなりすぎたり、枝が伸びすぎて樹形のバランスを崩したりしてしまうことがあるのです。そのため、こまめに剪定をおこない、丸い形や円錐形などといった人工樹形に整えることが多いのです。
それに対して、細く繊細な枝が伸びるアオダモの枝葉は密生することが少なく、成長が遅いので樹形も乱れにくい特徴があります。そのため、自然のままの姿が美しいアオダモは、剪定を頻繁におこなう必要はありません。
シンボルツリーで人気なアオダモ
アオダモは生命力が強く、病気にもなりにくいため手のかからない樹木です。成長が穏やかで大きくなりすぎることはあまりなく、頻繁な手入れも必要ないことがシンボルツリーとして人気のある理由といえるでしょう。枝が伸びてもすっきりとしていて圧迫感がないので、玄関や中庭などの狭いスペースで育てられるのも大きなポイントです。
アオダモを剪定するならどうしたらよい?
成長が遅いとはいえ、アオダモは10m~20mほどにまで成長することもあります。管理をしやすくするためには、大きさを調整する剪定をするとよいでしょう。ただし、自然樹形が魅力のアオダモは、極端に大きな剪定はしないのが基本です。不要な枝を取り除き、伸びすぎた枝を短くする程度にとどめておきましょう。
剪定をする時期は、アオダモの休眠期である12月~3月ごろが最適です。休眠期のアオダモは眠っていて体力をあまり使いませんので、枝を切っても負担が少ないのです。
アオダモのお手入れ
アオダモの成長には十分な日光が必要ですが、しっかりと根づくまでは乾燥に弱い性質があります。夏場などに日当たりが強すぎると乾燥して枯れてしまうことがありますので、午後には日陰になる半日陰か、明るめの日陰で育てるのがよいでしょう。
水やりは頻繁におこなう必要がなく、基本的には雨だけでも育ちます。ただし、落葉期ではないのに葉が落ちていたら、水が不足しているおそれがあります。土が乾いていたらたっぷりと水やりをしましょう。生命力が強いので肥料もそれほど必要ありませんが、冬に有機肥料を少量与えると成長がよくなります。
大きく育ったアオダモはプロの手で小さくしよう
もしもアオダモをしばらく放っておいて大きくなりすぎた場合、剪定をしてさっぱりしたいところですが、大きな剪定はアオダモに負担をかけ、弱らせてしまうこともあります。また、切ったところから枝が強く伸びて樹形を乱してしまうこともあるのです。大きさを調整するような強い剪定は、剪定のプロに任せるのがよいでしょう。
剪定の業者を探すなら、剪定お助け隊にご相談ください。お近くの剪定業者を無料でご紹介します。剪定お助け隊に加盟している剪定業者は庭木1本からのご依頼でも親切丁寧に対応していますので、ぜひお気軽にご相談してみてください。
アオダモの花が咲かない?枯れた?
アオダモを育てていく上で、なにかしらのトラブルが発生することも考えられます。そんなときにはどのように対処すればいいのでしょうか。アオダモの栽培で起こるトラブルと、その対処法をご紹介します。
花が咲かないけどどうして?

アオダモは4月から5月に雪の結晶のような白く繊細な花を咲かせます。アオダモを育てはじめて数年たつけれど、なかなか花が咲かないと首をかしげている人も多いようです。じつは、アオダモは5年に1度ほどしか花を咲かせないのです。これは成長の遅いアオダモの特性であってトラブルではありませんので、花が咲くのを気長に待ってみましょう。
また、あまりに何年も花が咲かないという場合や、咲き方が悪いという場合には、剪定で花芽を切ってしまったということもありえます。花芽は次の年に花になる新芽で、新しい枝の先に7月ごろにできはじめます。剪定でこの部分を切り落としてしまうと当然花は咲きませんので、剪定は花芽を確認して、切らないように注意しておこないましょう。
枯れてしまった!
アオダモは根づくまでは乾燥に弱く、日が当たりすぎると乾燥して枯れてしまうことがあります。その場合は十分に水をやって、様子をみましょう。
また、反対に水が多かったり土壌の水はけが悪かったりすると、根腐れをすることもあります。枯れてきた原因が根腐れの場合は、可能であれば一度アオダモを地面から掘り返し、腐った根を取り除いて水はけのいい場所に植え替えるのがよいでしょう。
害虫の被害にあっていることも考えられます。アオダモは病害虫に強い樹木ですが、まれにカミキリムシやその幼虫が発生することがあります。カミキリムシの幼虫はテッポウムシとも呼ばれ、木に穴を開けて内部を食い荒らしてしまうのです。
カミキリムシは園芸用の殺虫剤を散布したり、幼虫のいる穴に針金などを入れたりといった方法で駆除することができます。カミキリムシは木の枯れたところや腐ったところに産卵するので、このような枝があれば早めに剪定をして取り除いておくことが大切です。アオダモの剪定時には、切り口が腐らないように癒合剤を塗っておきましょう。
アオダモ以外にもある!人気のシンボルツリー
アオダモ以外にも、シンボルツリーにできる樹木はたくさんあります。ここで、シンボルツリーにする樹木を選ぶ際のポイントも解説しておきます。
・大きさ
シンボルツリーには家の目印としての役割があり、玄関先などに植えることも多いでしょう。玄関先のスペースは限られることが多いので、小さくまとめることができる樹木が向いています。
クチナシやツツジなどの低木であれば、あまり大きくならないので管理もしやすいでしょう。その木がどれくらいの大きさに成長するのかを事前に確認しておくことが大切です。
・株立ちと単幹
横に広がる株立ちの樹木は、玄関の目隠しや日除けとしても使えます。株立ちで育てることができる樹木には、ヒメシャラやシマトネリコなどがあります。1本の太い幹が伸びる単幹の樹木は株立ちに比べて低価格ですが、大きく育つものが多いため、剪定などのこまめな手入れが必要です。単幹の樹木にはハナミズキ、コニファーなどがあります。
・常緑樹と落葉樹
樹木には常緑樹と落葉樹がありますが、シンボルツリーをどのように楽しみたいかによって、どちらが適しているかは変わってくるでしょう。年中緑を楽しみたいなら常緑樹、紅葉や落葉といった季節の移ろいを感じたいのなら落葉樹が向いています。
・縁起のよい木
家を建てたときや子どもが生まれたときなどに記念として植えるのであれば、縁起のよい木を選ぶのもよいでしょう。たとえばナンテンは「難を転じる」という語呂あわせから縁起がよいとされています。ユズリハは新しい葉と入れ替わって古い葉が落ちることから、子どもが財産を受け継ぎ、子孫繁栄を願う意味で植えられることがあるようです。
お手入れはめんどう、忙しい…そんなときは剪定のプロがお手伝いします
ある程度の大きさになる木であれば、ちょうどよい大きさを維持するためには剪定が必要です。また、剪定には病害虫の予防といった効果もあるので、こまめにおこなったほうが樹木のためにもよいでしょう。
しかし、そう頻繁に手をかけていられないということもあるでしょう。剪定の方法がわからなくて、失敗して枯らせてしまったら嫌だという不安もあるかもしれません。
そんな場合には、プロに任せる方法があります。剪定業者はそれぞれの樹木の性質をよく理解していて、適切な方法で剪定をしてくれます。樹木の健康を守り、美しい樹形を作ることもできるのです。
剪定業者の探し方がわからないのなら、剪定お助け隊が力になります。24時間無料の電話相談を受けつけていますので、相談していただけば内容に応じたふさわしい業者を無料でご紹介します。シンボルツリーを美しく維持していくために、剪定お助け隊を活用してみてください。
剪定の関連記事
- タラの木強剪定|正しい方法で収穫量アップ!基本の育て方・水耕栽培
- ベニカナメモチは生垣に最適!鮮やかな赤色の新芽を存分に楽しむ方法
- つつじの育て方のポイントは日光!正しいお手入れで花を咲かせよう!
- コニファーの剪定にはさまざまな効果が!健康と景観を保つ剪定のコツ
- ユッカ剪定のキホンまとめ|正しい剪定とお手入れで健康的に育てよう
- ヒメシャラの育て方は簡単!特徴と美しく元気に育てるためのポイント
- ピラカンサ剪定|巨大化してトゲが脅威になることも!適切なお手入れ
- ユーカリ剪定の基礎を解説!正しい剪定には健康と美しさを保つ効果が
- ビバーナムティヌスの剪定はタイミングが重要!剪定方法と育てかた
- 萩の剪定には季節ごとのやり方がある!育てかた・増やしかたも解説