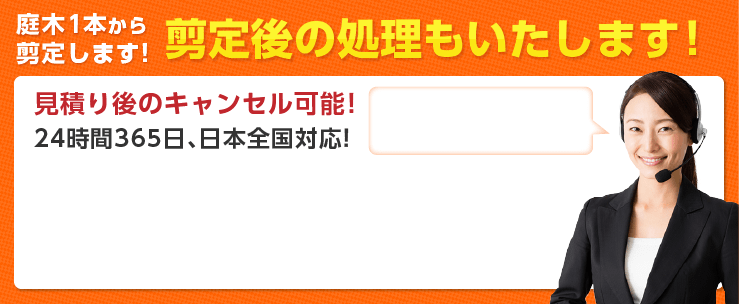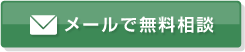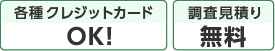【症状別】シマトネリコの病気・害虫の見分け方|枯れていないかも?

シマトネリコは病気や害虫に強い庭木ですが、それでも場合によって葉が抜け落ちたり、枝が枯れたりします。シマトネリコが落葉したり枯れたりする原因は複数あり、対策方法も原因ごとに異なります。原因を判断する方法や適切な対策を知り、健康的なシマトネリコを目指しましょう。
この記事では、シマトネリコに異変が起きたときの原因と、症状ごとの対策について紹介しています。また、シマトネリコが病気や害虫にかかりにくくするための予防法についても載せてあります。最後まで読めば、シマトネリコをずっと健康的に育て続けることも夢ではないでしょう。
目次
シマトネリコの様子が変!原因と判断のしかた
シマトネリコに異変を感じたときは、まず症状を確認しましょう。シマトネリコに元来備わっている性質が、異変の原因である可能性もあるのです。その場合は、様子が変であってもとくに慌てることもありません。しかし、原因と判断方法を知らなければ、落ち着いて対処することも難しいです。そのため、シマトネリコについての見識を深めましょう。
ここでは、シマトネリコの様子が変わる原因とされている「シマトネリコの性質」「水・肥料の過不足」「病害虫」について見ていきます。
本当は問題ないかも!冬の時期の異変は様子見を

気温が低下する冬の季節になると、シマトネリコは落葉したり葉が赤くなったりすることがあります。落葉や葉が赤くなるのは、シマトネリコの性質であり、春になればまた元どおりになることが多いです。
しかし、寒くない時期に落葉や葉の変色が起きている場合は、性質のせいというわけではない場合があります。性質だろうと判断して放置していると、状態がより悪くなってしまうおそれがあるため、別の理由を考えるようにしましょう。
水や肥料の過不足
シマトネリコに与える水や肥料が適切でないと、生育を悪化させて枯れさせることがあります。水のやりすぎは根腐れを起こしますし、水の量が少なくても水分不足で枯れてしまいます。
また、肥料が多すぎると、肥料焼けによって水分が外へ流れ出のです。しかし、肥料焼けの状態にさせないために肥料を与えないでいると、栄養不足でシマトネリコが弱ってしまうこともあるでしょう。もし、水や肥料の過不足を疑うときは、水やりと肥料やりのタイミングや量を見直してみましょう。水やりや肥料の与え方については、記事内で後述します。
病害虫の被害にあっている
シマトネリコは病気や害虫の被害にあうと、生育を阻害されて枯れることがあります。ほとんどの病気は、被害にあった部分から周りへ感染していきます。また、害虫は放っておくと繁殖するばかりなので、病害虫被害が起きたときは早めに対処しましょう。病害虫への対策については、記事内で後述します。
枝を折れば枯れているかがわかる
シマトネリコが枯れているかどうかを調べたいときは、枝を折ったときの音から判断できます。枯れた枝は乾ききっているので、枝を折ったときにバキッという乾いた音が鳴るのです。もし勢いよく折れなかったり、枝の断面が緑色だったりした場合は、まだ枯れていないといえます。
ただし、枝を折って判断するこの方法には、注意が必要です。なぜなら生きている枝を折るということは、シマトネリコにダメージを与えることだからです。何度も枝を折って確認するのはおすすめできません。そのため、枯れを確認する箇所は、枯れの疑いがある場所だけにしておきましょう。
【症状別】シマトネリコの病気と害虫・対策
シマトネリコに病気や害虫被害が発生したときは、原因ごとに適した対策をとることが大切です。シマトネリコが病害虫被害を受けたときには、一般的に「葉に斑点がある」「幹に穴や欠けがある」「丸い虫がついている」「葉が丸まっている」といった症状が現れます。ここでは、それらの原因と対策について見ていきましょう。
葉に斑点がある

葉に黒い斑点がある場合は「すす病」に、白い斑点がある場合は「うどんこ病」にかかっている危険性が高いです。すす病に感染していると、黒い粉状のカビに葉が覆いつくされてしまい、シマトネリコが活動するために重要な光合成や蒸散がおこなえなくなります。
また、うどんこ病に感染している場合も、白いカビ菌に葉の表面を覆われてしまうことになるため、すす病と似たような被害が発生します。
すす病やうどんこ病にかかった部分は、元の正常な状態には戻せないことが多いので、感染した箇所を切り取って健康的な枝や葉を守ることが大事です。また、予防するには、病原菌の活動を抑えるために殺菌剤をまく方法があります。
幹に穴があいている・かじられている
シマトネリコの葉や幹が、穴があいていたり欠けていたりするときは、「コウモリガ」が近くにいるかもしれません。コウモリガは、シマトネリコの幹を食べながら中に侵入してきます。被害があった箇所から先は、根から吸収した栄養がうまく渡せなくなって枯れることがあるのです。
対策としては、コウモリガ用の薬剤をまく以外にも、シマトネリコ周辺の雑草を取り除く方法があります。コウモリガは雑草を食べて成長したあとに、シマトネリコの幹や葉を食べるようになるので、除草しておけば成長を抑えることができます。
丸い虫が張り付いている
シマトネリコに張り付いている白色や黒色の丸い虫は、「カイガラムシ」という害虫です。カイガラムシはシマトネリコの樹液を吸って、生育を悪化させます。また、カイガラムシの排泄物は、すす病などの病気にかかりやすくする性質があるので、早めに対処するのが望ましいです。対処方法としては、ブラシでこするか、箸などを使ってつまみ取りましょう。
葉が丸まっている
シマトネリコの葉に丸まっている部分があれば、「ハマキムシ」の被害が考えられます。ハマキムシはシマトネリコの葉だけでなく、新芽も食べてしまう害虫です。棒などで潰して駆除するか、殺虫剤をまいて対処しましょう。
このように、シマトネリコがかかる病気は複数の種類があります。もし、それぞれの病害虫の判断や、対策がわからないときは剪定業者に任せれば、解決できることがあります。剪定業者のなかには、木の剪定をおこなうだけでなく、病害虫対策のサービスを提供しているところもあるのです。
とくに弊社では、病害虫対策のための消毒や、病気にかかった木の伐採なども依頼することができます。弊社について何か気になることがありましたら、無料の電話相談にてお気軽にお聞きください。
シマトネリコにかかせない【予防・お手入れ】まとめ
シマトネリコを健康的に育てるには、日頃からおこなう予防や手入れをおこなうことが大事です。とくに重要なシマトネリコの剪定や肥料やり、水やりの正しいやり方について見ていきましょう。
シマトネリコの剪定

剪定して日当たりや風とおしをよくすることは、シマトネリコを健康的に育てるためにかかせません。風とおしがよいと湿気がたまりにくくなり、シマトネリコは病気や害虫被害にあいにくくなります。また、日当たりをよくしておくと、シマトネリコの光合成が盛んになるので、元気に育ちやすくなるでしょう。
剪定する枝はおもに、密集している枝や伸びすぎている枝です。枝わかれしている根元から、剪定ばさみで切り落としましょう。また、枯れている枝や古い枝も取り除きます。
剪定する時期は3~4月ごろや6~7月ごろと、9~11月ごろの年3回です。ただし、6~7月ごろは花が咲きますので、シマトネリコの花を見たい場合は剪定を控えておきましょう。
肥料やり
2月ごろに緩効性肥料を与えておくと、シマトネリコの芽のつき具合をよくしたり、1年間弱りにくくしたりできます。緩効性肥料はゆっくりと栄養が溶け出す肥料なので、2月ごろに与えると、生育が活発になる春や夏ごろまでに栄養を蓄えられるのです。
水やり
シマトネリコは自然に降る雨で水をまかなえることが多いので、基本的には水やりをしなくても育ちます。ただし、夏場の日差しが強い時期は地面が乾燥しやすいので、水不足を起こすことがあります。夏場は地面の表面が乾燥しているかを確認して、乾いていたら水やりをおこないましょう。
迷ったときは業者へ
シマトネリコの手入れ予防方法で困ったときは、業者に任せれば解決してくれることが期待できます。
とくに剪定については、業者に一度やってもらえばシマトネリコの生育が改善されますので、その後の管理が楽になるでしょう。また、「業者に依頼すると費用が心配……」という方は、見積りで具体的な作業内容や費用を確認することができます。
弊社では肥料やりや、庭の除草などのサービスもおこなっていますので、依頼者のお困りごとに合わせて柔軟に対応できます。また、見積りについても無料で受け付けていますので、納得がいかない作業内容や費用の場合はキャンセルすることも可能です。
お試しでの見積りも歓迎していますので、ぜひ弊社のサービスを利用してみてください。お電話お待ちしております。
剪定の関連記事
- びわの育て方を間違うと実が収穫できないかも!?剪定・摘果は重要!
- ヤマモモの剪定|実を安定させるお手入れ・時期・樹形づくり
- コニファーの剪定にはさまざまな効果が!健康と景観を保つ剪定のコツ
- シャクナゲの剪定と育て方|基本の方法と植え替え・増やし方も紹介中
- ツツジの剪定方法をチェック!剪定のタイミングは開花時期に合わせて
- 椿の育て方|初心者も失敗なし!椿を存分に楽しむ方法をご紹介します
- モッコクの剪定方法を解説!時期・切り落とす枝の見極めが重要
- みかん剪定は幼木と成木でやり方が違う!適期や作業時の注意点
- ハナキリンは剪定が必須!正しい剪定方法とハナキリンの増やし方
- ヤツデの剪定と育て方|大きな葉と白い花が特徴!縁起物の人気植物