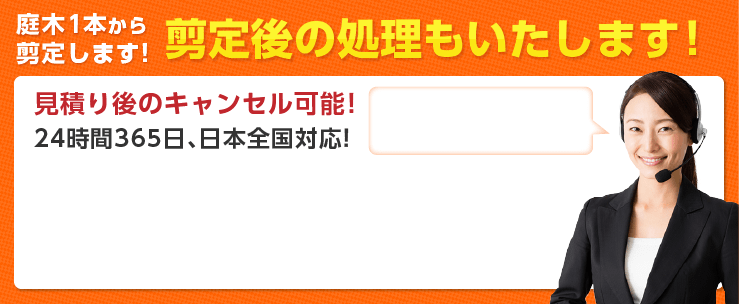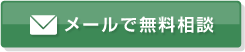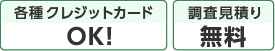レッドロビンが病気かも?放置すると枯れてしまう!確認・対処・予防

レッドロビンは美しい赤い葉が特徴的な樹木です。しかし、その美しい葉を台なしにしてしまう病気があります。病気になった葉を放置していると、病気が広がったり木が枯れたりしてしまうことも……。
病気の葉は見つけたらすぐに取り除き、そして適切な予防をしてレッドロビンを守ってあげましょう。このコラムを読んで、レッドロビンがかかりやすい病気、病気になってしまったときの対処法や予防法を詳しく知っていきましょう。
目次
レッドロビンが病気かも!まずはここを確認しよう
レッドロビンの葉に小さな斑点ができ始めたら要注意です。“ごま色斑点病”や“褐斑病(かっぱんびょう)”という病気にかかっているおそれがあるからです。それぞれの症状や、レッドロビンがこのような病気にかかってしまったときの対処法を確認していきましょう。
レッドロビンがかかりやすい病気

ごま色斑点病も褐斑病も、どちらもカビの一種によって引き起こされる病気です。このような病気にかかってしまった葉は、見た目も悪いですし、進行すると葉が枯れたり落ちたりしてしまいます。
ごま色斑点病も褐斑病も、カビによって引き起こされる点は一緒なので、対策や予防法にも大きな違いはありません。
しかし、今後薬剤を使用するなどして対策する際には病名がわかっていたほうが便利なこともあるでしょう。以下にごま色斑点病と褐斑病、それぞれの斑点の状態をまとめるので、病名が知りたいときの参考にしてください。
【ごま色斑点病】
斑点の状態:斑点の周辺は紫から赤色。かさぶた状の黒い点ができる。
【褐斑病】
斑点の状態:褐色の小さな丸い斑点ができ始め、色が濃くなったり斑点が大きくなったりしていく。
病気の葉は取り除く
ごま色斑点病や褐斑病といった病気にかかった葉は、気づいたときに取り除いてください。また、病気で落葉して株元に落ちている葉も忘れずに取り除きましょう。病気の葉から周辺の葉や植物にカビの胞子が移り、病気が広がっていくのを防ぐためです。
まわりの健康な葉や植物を守るためにも、病気が疑われる葉は早めに取り除き、燃えるゴミとして処分してしまいましょう。
放置したらどうなるの?
病気の葉を放置して適切な対応をせずにいると、先述のように病気がまわりの葉や植物に広がっていくおそれがあります。症状が進行すると、ほとんどの葉が落葉して丸坊主になってしまうこともあるようです。
レッドロビンのせっかくの美しい赤色の葉を楽しむことができなくなってしまったら残念ですよね。そうなる前に、病気の葉はきちんと取り除きましょう。
とはいえ、自己判断で対処するのは不安…
病気の葉をそのままにしておいてはいけないとわかっていても、自己判断で対処して失敗してしまったらどうしようとお悩みの方もいらっしゃるでしょう。そんなときは、お庭や木々のプロに相談してみましょう。
悩んでいる間にも病気が進行・拡大してしまうかもしれません。「どこまで取り除くべきかわからない」「病気の葉を全部取り除いたら不格好になってしまいそう」……そんなお悩みは、私たち“剪定お助け隊”までどうぞお気軽にご相談ください。
病気の葉をきちんと取り除くように剪定しつつ、できるだけ美しい姿を保つことができるよう尽力いたします。
レッドロビンを病気から守る!4つの予防策
ごま色斑点病や褐斑病はカビの仲間が発生の原因となるので、カビの繁殖を防ぐことで予防効果が期待できます。カビの繁殖を防ぐためには、殺菌剤の利用や多湿状況を避けるといった方法があります。
どうすればレッドロビンの病気を予防できるのか、具体的な方法をみていきましょう。
1.殺菌剤

レッドロビンの病気の原因となるカビとは“菌”の一種ですから、殺菌剤を散布することで病気の予防効果を見込めます。殺菌剤は、雨によってカビが発生しやすくなる梅雨時期を中心に散布するとよいでしょう。
また、殺菌剤はホームセンターやインターネットで購入できるので、予算や効果、使い方などをふまえて選んでください。購入した殺菌剤を使用する際は、使用方法や注意事項を守って散布しましょう。
2.土壌改良
レッドロビンを植えている土の水はけが悪く、よく湿っているような状況ならば、水はけのよい土に入れ替えてみるとよいでしょう。カビは多湿な環境下で繁殖しやすいからです。
また、レッドロビンは栄養の豊富な土を好みます。このような、肥料分の多い水はけのよい土で育てることで、病気にかかりにくい健康な状態に成長させることが可能です。
3.剪定
剪定によって混み合った枝葉や樹形を乱す枝葉を切り落とし、風通しや日当たりを改善しましょう。詳しい剪定の方法については後ほどご紹介します。
4.植え付けの間隔
これから新しく木や植物を植えたい方は、植え付けの間隔に余裕を持つように意識しましょう。その植物が成長するとどのくらいの大きさになるか事前に調べておき、十分な間隔をあけて植え付けてください。植え付けの間隔を十分にとっておくことで、枝葉が混み合い、多湿環境になってしまうことを防げます。
レッドロビンをより赤くより美しく育てるコツ
レッドロビンは常緑性で、1年を通して色づいた葉を楽しむことができます。レッドロビンといえば、あざやかな赤い葉が印象的ですね。この美しい赤い葉を楽しみに育てている方も多いでしょう。そんなレッドロビンをより美しく育てるコツをご紹介します。
レッドロビンはどんな樹木?

まずはレッドロビンの基本的な情報をおさらいしていきましょう。レッドロビンの生態を知っておくことで、日々のお手入れに活用できます。
【レッドロビン】
- カナメモチ属
- 常緑性
- 原産地:アメリカ
- 開花期:4~6月
- 樹高:3~10mほど
レッドロビンは日当たりのよい場所を好みます。水やりはあまり必要なく、雨水で十分でしょう。
成長が早いことが特徴的で、樹高10m以上に成長することもあります。刈り込みにも強い丈夫さから生垣として利用されることが多いです。
レッドロビンといえば赤い葉が特徴的ですが、赤くなるのは新芽のみです。新芽を出すためには定期的に剪定する必要があります。ただし、赤い葉を維持するために剪定することで、花芽が刈り取られて開花しないということも多いようです。
レッドロビンの剪定方法
レッドロビンの赤い葉を楽しむためには、定期的に剪定して新芽を出すことが大切です。また、成長が早いので、高く伸びすぎて手に負えなくなってしまう前に剪定してあげましょう。
ここからは、レッドロビンの剪定方法やコツをご紹介します。
【剪定時期】
年に2~3回、春・初夏・秋を目安に定期的に剪定してあげましょう。レッドロビンは丈夫な樹木なので、太い枝を切り落とすといった強い剪定をしても枯れにくいです。そのため、剪定時期にはこだわりすぎず、枝葉が伸びてきたらこまめに剪定するとよいでしょう。
【剪定のコツ】
レッドロビンは生垣として育てている方が多いので、ここでは生垣として仕立てる剪定方法をご紹介します。
レッドロビンは上へと成長する力が強いので、上部の葉が混み合いやすいです。伸びた上部を中心に、刈り込みバサミや剪定バリカンでお好みの形に切り整えていきましょう。
先述のように、ごま色斑点病や褐斑病を防ぐためには日当たりや風通しといった要素も大切です。基本的には定期的に好きな形に刈り込むだけでよいのですが、レッドロビンの健康も考えつつ美しく整えたいなら、剪定のプロに相談するのもおすすめです。
剪定をプロに任せるべきとき
レッドロビンは丈夫な樹木なので、剪定初心者の方でも木を枯らしてしまうような大きな失敗はしづらいでしょう。しかし、レッドロビンをこだわりの形に整えて楽しみたい場合、単純に伸びすぎた枝葉を切り落とすよりも難易度が上がります。樹形にこだわりがある方は、剪定のプロにお任せしてみてはいかがでしょうか。
さらに、レッドロビンの花を楽しみたいときと赤い新芽を楽しみたいときでは、剪定のコツに違いがあります。このような複雑な剪定をしたいときもプロの知識や技術が必要です。
また、レッドロビンは成長が早い樹木です。少し剪定をしない間に大きくなってしまってしい「剪定したいけれど手が届かない!」というときもプロの出番です。
無理な姿勢で剪定して、はさみや落ちてきた枝葉が目に入ってケガをしたり、脚立から落ちたりといった事故も考えられます。大きくなりすぎたレッドロビンは、プロに剪定をお願いしましょう。
- レッドロビンの樹形や花つきにこだわりたい!
- レッドロビンが大きくなり、自分で剪定するのは大変……
このようなときは、ぜひ“剪定お助け隊”までご相談ください。ご予算やこだわりの条件をお伝えいただければ、全国の加盟店の中からお客様にぴったりの剪定のプロを派遣いたします!
剪定の関連記事
- ハナキリンは剪定が必須!正しい剪定方法とハナキリンの増やし方
- 剪定ばさみの手入れ!研ぎ方や使う道具・調整方法・劣化原因まで解説
- ケヤキの剪定方法と依頼したときの費用!盆栽での剪定もご紹介します
- ソテツ剪定でさわやか南国ムード復活!目的別の対処法&育て方のコツ
- びわの種の育て方~種まきから日ごろのお世話、剪定まで~
- ツツジの剪定方法をチェック!剪定のタイミングは開花時期に合わせて
- ぶどうの育て方を徹底解説!肥料のあげ方も剪定方法もこれで丸わかり
- ヤマボウシの剪定をして元気に育てよう!剪定時期・方法をご紹介
- 剪定ばさみの選び方|使いやすい道具選びは剪定上手さんへの第一歩
- コニファーの剪定は初心者でもできる!ちょっとしたコツをご紹介