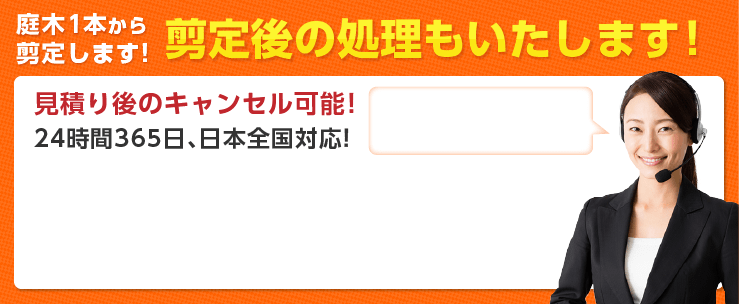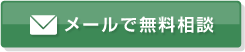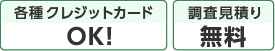幸福の木(ドラセナ)の剪定と育て方|初心者OK葉を楽しむ観葉植物

幸福の木と呼ばれるドラセナは、室内のインテリアとして人気です。幸福の木は比較的管理がしやすく、育てやすい観葉植物であるということが、大きな理由といえます。樹木には剪定などのお手入れが欠かせませんが、幸福の木にはそれほどこまめな剪定が必要ないのです。
ただし、幸福の木を育てるのにはいくつか注意点もあります。このコラムでは、幸福の木の剪定や育て方を解説します。育てるのに必要な環境やお手入れを理解することで、健康で美しい幸福の木を維持していくことができるでしょう。
目次
幸福の木(ドラセナ)の切り戻し剪定について
幸福の木は基本的に、それほど頻繁な剪定は必要ありません。ただ、お手入れのひとつとして2~3年に1度は剪定をすることで、きれいな樹形と木の健康を維持することができます。ここでは、幸福の木の剪定について解説します。
剪定の意味と必要性

剪定とは、おもに木の枝を切って整えるお手入れです。木を剪定することには、以下のような理由があります。
・大きさを調整する
幸福の木は上に向かって伸び続ける性質があり、放っておくとどんどん大きくなってしまいます。室内で育てている幸福の木があまり大きくなりすぎるとスペースを取り、ほかのインテリアとのバランスも悪くなってしまうでしょう。木の枝を適切な長さに切ることで、管理しやすい大きさに維持することができるのです。
・枝数を増やす
自然の状態では、幸福の木は幹を上に伸ばすだけで、枝や葉の数は増えていきません。剪定で枝を切ると、切った部分のわきから新しい枝が生えて枝が増えていきます。枝を増やすことで、葉が生い茂った見栄えのよい樹形を作ることができるのです。
・日当たりと風通しをよくする
枝葉が増えすぎると木の内側に日陰ができ、日当たりが悪くなります。風通しも悪くなるので湿気がこもり、害虫が発生したり、カビなどが発生して病気になったりすることもあるのです。剪定をして枝葉の数を適度に減らし、日当たりと風通しをよくすることで、木の健康を保つことができます。
剪定の時期と方法
剪定には、おこなうのにふさわしい時期があります。幸福の木の剪定に最適な時期は、5月~6月ごろです。日差しの強い真夏や寒い冬に剪定をすると、木が弱ってしまうことがあるので注意しましょう。
5月~9月ごろになると、幸福の木は枝葉を伸ばす成長期に入ります。元気のあるこの時期に剪定をすることで木への負担が少なく済むのです。剪定後に木が十分に回復できるよう、成長期の前半におこなうのがよいでしょう。
剪定は切り戻しという方法でおこないます。伸びすぎた枝をちょうどいい長さのところでカットするのです。カットするときには、枝についている新芽の少し上でカットするようにしましょう。新芽は枝のこぶのように出っ張っているところにあります。新芽を残してカットすることで、新しい枝が生えてきてきれいな樹形になります。
幸福の木の葉は枯れても落ちない性質がありますので、変色してしまっている葉は手やハサミで摘み取ります。部分的に変色している葉は変色している部分をカットして、見栄えがよくなるように葉先を三角形に整えましょう。
幸福の木を上手に育てるには、剪定のほかにもいくつかポイントがあります。次の章では、幸福の木の育て方について解説します。
幸福の木(ドラセナ)の育て方
幸福の木は観葉植物として、室内で育てることが多いでしょう。ここでは、室内で育てる場合の注意点やポイントをご紹介しますので、参考にしてみてください。
育てるのに適した環境

幸福の木は日陰でもある程度育ちますが、日当たりがよい場所のほうが葉の色づきがよくなります。日の当たる窓辺やベランダに置いておくのがよいでしょう。ただし、真夏の強い日差しが当たり続けると弱ってしまうこともあります。レースのカーテンを閉めて遮光するか、夏の間は日陰に移すとよいでしょう。
もともと熱帯地域の植物である幸福の木は寒さに弱い傾向がありますので、ベランダで育てているなら、冬の間は室内に入れるのがよいでしょう。ただし、エアコンの風が直接当たっていると乾燥して弱ってしまいますので、置く場所には注意が必要です。
水やりと葉水(はみず)
5月~9月の成長期には、水やりがとても大切です。土が乾いたら鉢の底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりをしましょう。ただし、真夏の気温が高いときには、土の中の水の温度が上がって根が弱ったり、蒸発した水蒸気にあたって葉が弱ったりといったことがあります。夏場の水やりは朝や夕方の比較的涼しい時間帯におこなうのがよいでしょう。
冬場は幸福の木の成長が止まり、あまり水を必要としなくなります。この時期に水やりをしすぎると根が蒸れて根腐れを起こすことがありますので、土が乾いて2~3日してから水をやる程度で十分です。
観葉植物のお手入れには、葉水も重要です。霧吹きなどで葉に水をかけます。葉水には葉焼けや乾燥を防ぎ、ホコリを落とす効果があります。高温多湿の熱帯地域の植物である幸福の木は葉の湿度を保つことで元気がよくなり、葉の色つやがよくなる効果もあるのです。
植え替え
水やりをしたときに、水があまり土に染み込まないようになったら、鉢の中が根でいっぱいになっている可能性があります。そのままだと水を十分に吸収できなくなりますので、ひと回り大きな鉢に植え替えましょう。
植え替えは、幸福の木の成長期である5月~9月におこなうのが最適です。これも剪定と同様に、木に十分に体力があるときのほうが、環境の変化に耐えられるからです。ただし、日差しが強い時期に植え替えをすると弱ってしまう場合もありますので、真夏は避けたほうがよいでしょう。植え替えは、次の手順でおこないます。
【植え替えの手順】
- 新しい鉢に底石と土を入れておきます。
- 幸福の木を古い鉢から引き抜き、根についた土を3分の1ほど落として根をほぐしましょう。
- 幸福の木を新しい鉢に入れたら、上から土を入れて隙間をふさぎます。
- 最後に鉢を少しゆすりながら水をやり、土と根をなじませます。
- 植え替え直後はあまり強い日に当てないように、明るめの日陰に置いておきましょう。
害虫
幸福の木にはハダニ、カイガラムシなどの害虫が発生することがあります。これらの害虫は幸福の木の養分を吸い取ってしまいます。
ハダニの発生を防ぐには、葉水が有効です。ハダニは水分を嫌いますので、こまめに葉水をして葉を湿らせておくことで寄りつかなくなります。カイガラムシは暗くて風通しの悪い環境で発生しやすくなります。枝葉が混みあっているときには、剪定をして日当たりと風通しを調整しましょう。
また、害虫の被害にあった枝葉は放っておくと病気になり、そこから病気が広がって木全体が枯れてしまうこともあります。そうならないために、被害にあった枝葉を剪定で取り除くことも大切です。幸福の木を剪定することには、害虫から木を守る効果もあるのです。
観葉植物として人気のある幸福の木ですが、育てる環境に注意が必要な樹木でもあります。次の章では幸福の木の特徴についてご紹介します。
幸福の木(ドラセナ)とはどんな木?
これから幸福の木を育てたいと考えているなら、幸福の木の特徴を理解しておく必要があるでしょう。どんな樹木を育てようか迷っている人は、以下を参考にしてみてください。
ドラセナが幸福の木と呼ばれる由来にはさまざまな説があります。有力なのは、ハワイで「幸福の木」と呼ばれているコルジリネ・ターミナリスという樹木と似ているからという説です。本来の「ハワイの幸福の木」は日本で育てるのは難しいことから、見た目の特徴が似ているドラセナが日本では幸福の木として広まったといわれています。
幸福の木ことドラセナは、熱帯アジアやアフリカなどの熱帯地域に自生する常緑樹で、およそ50種の品種があります。種類によって樹高が2mほどにおさまるものもあれば、20mほどまで成長するものもあるのです。
大きく成長する種類の幸福の木をお庭で育てたいという人もいるかもしれませんが、庭植えで育てられるのは「ドラセナ・ドラコ」などのごく一部の品種に限られます。寒さに弱い幸福の木を庭植えで育てるのは難易度が高いでしょう。
冬場だけ鉢に植え替えて室内で育てるという方法もありますが、お庭から鉢に植え替えをするのはかなりの手間です。大きく育ってしまうとそれも難しくなります。もしもお庭に木を植えて育てたいと考えているのなら、ほかの樹木を選んだほうが無難かもしれません。
庭木の剪定なら弊社におまかせください!

お庭に植えるなら、ある程度の大きさのある樹木を植えたいと思うでしょう。室内で育てられる幸福の木などは剪定のお手入れも比較的簡単ですが、庭植えの場合は少し面倒です。大きな樹木は管理が難しく、剪定にも手間がかかります。しかし放っておくと大きくなりすぎて、手に負えなくなってしまうこともあるのです。
剪定が難しいと感じたら、剪定業者に任せるのもひとつの解決策です。剪定業者に任せてしまえば手間も省けますし、失敗して枯らせてしまう心配も少なくなるでしょう。剪定業者を探す際には、ぜひ弊社にご相談ください。弊社に加盟している多数の剪定業者のなかから、最適な業者を無料でご紹介します。
剪定の関連記事
- プルーンの剪定・手入れ方法まとめ|基本をマスターして目指せ収穫!
- 庭木の剪定は重要な作業!剪定の必要性・方法・時期などをご紹介
- ピラカンサ剪定|巨大化してトゲが脅威になることも!適切なお手入れ
- ハイビスカスの剪定時期や方法をご紹介!きれいな花を咲かせましょう
- ケヤキの剪定方法と依頼したときの費用!盆栽での剪定もご紹介します
- レッドロビンの剪定方法とは?お手入れのコツや美しい生垣を保つ秘訣
- ユーカリ剪定の基礎を解説!正しい剪定には健康と美しさを保つ効果が
- アオギリの剪定時期は地域によって違う!?やり方・ポイントを解説
- 【キンメツゲ】はどんな木?きれいな生垣をつくる5か条を解説!
- 庭木の剪定をプロにまかせる!プロ集団があなたの庭をお助けします!