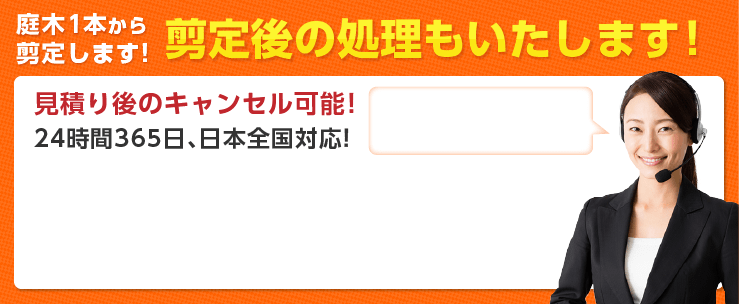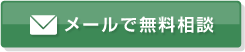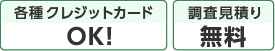カポックの剪定~剪定後のお手入れまで|元気に育てる秘訣まとめ

カポック(シェフレラ)は観葉植物として人気のある植物です。そんなカポックは生長が早いため、樹形を整える・風通しをよくして病害虫の発生を防ぐといったことのためにも、カポックを適度に剪定することが重要です。
しかし、「剪定をどうやっておこなったらよいかわからない」「剪定をはじめておこなうので不安」という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここではカポックの剪定方法をご紹介します。また、剪定したカポックの枝の活用術や元気がない原因についてもご説明します。ぜひこの記事を読んで、カポックの健康維持にお役立てください。
目次
カポック剪定~剪定後のお手入れまとめ
まずはカポックの剪定方法や、剪定後のお手入れについてご紹介します。以下の内容を参考にして、正しい方法でカポックの剪定をおこなってください。
剪定は「春」がおすすめ

カポックの剪定は春におこなうのがおすすめです。カポックはいつ剪定をおこなってもかまいませんが、春におこなうことで株が弱るのを防ぐことができます。具体的には、5月~7月に剪定をおこなうとよいでしょう。
「完成形」をイメージして剪定を!
カポックは丈夫な植物のため、多くの枝を切ってもダメージを受けにくいです。そのため、剪定ではお好みの樹形にすることが可能です。剪定に取り掛かる前に完成形をイメージしておくとよいでしょう。
そして、伸びすぎた枝を切りながら理想の形に仕上げていってください。樹形をコンパクトにしたい場合は、生え際から10~20cm程度残して枝を切ると、切り口のすぐ上から新しい芽が伸びてまとまった樹形になります。
お手入れ:育てる環境を整えよう
カポックは、直射日光が当たると「葉焼け」してしまうおそれがあります。葉焼けとは、葉が焼けてしまって変色してしまうことです。葉焼けは植物が弱る原因にもなるので、それを防止するためにも室内ではレースのカーテン、屋外では遮光ネットや寒冷紗などで直射日光が当たらないようにしてください。
お手入れ:水やりと肥料の頻度は?
カポックは乾燥に強い植物なので、少しなら水やりを忘れても大丈夫でしょう。ただし、水やりをまったくおこなわないと、枯れるおそれがあります。
また、冬は生長が止まる時期なので、土が乾いて、さらに3~4日経ってから水を与えるようにしてください。水を与えすぎると「根腐れ」を起こす原因にもなります。根腐れとは、その名のとおり根が腐ってしまうことで、酸素不足が原因で起こります。根腐れを起こさないためにも、水の与えすぎには注意してください。
また、肥料は4月~10月に3~4回程度、緩効性肥料をあげるのが効果的です。緩効性肥料とは、じっくりと効果を現わす、持続性が高い肥料です。カポックは緩効性肥料を与えることによって、新芽や花芽を増やすことができたり、株を健康的に育てたりすることができます。
お手入れ:病害虫対策をしよう
カポックを育てるうえで忘れてはならないのが、病原虫対策です。カポックが被害にあいやすい病害虫は「ハダニ」「カイガラムシ」「うどんこ病」などです。
ハダニやカイガラムシは、植物の汁を吸う害虫です。汁を吸われた害虫は、うまく生長することができず、最悪の場合枯れてしまいます。
また、うどんこ病とは、白い粉がふりかかったようになる病気です。白く覆われた部分は光合成をおこなうことができないため、株が弱ってしまう原因となります。
病害虫で弱った部分は早めに剪定をおこなって被害の拡大を防ぎましょう。病害虫の予防にも剪定が有効です。病害虫は湿度の高い場所で発生しやすいので、風通しをよくして湿度を下げることで防ぐことができるのです。
もし、「自分で剪定をおこなえる自信がない」「剪定方法がわからない」という方がいれば、剪定業者に相談してみることをおすすめします。業者に依頼すれば、経験や技術が豊富なスタッフが作業をおこなってくれるので、失敗する心配もありません。
弊社では、全国多数の加盟店の中から、カポックの剪定をおこなう業者をご紹介します。もしカポックの剪定にお困りの方がいれば、弊社までご連絡ください。
剪定した枝・茎の利用法|カポックをさらに楽しもう!
カポックの枝には、さまざまな活用法があります。そこで、ここからは、カポックの剪定した枝の活用術をお伝えします。以下の内容を参考にして、カポックをより楽しんでみてください。
【1】水挿し

剪定したカポックの枝を使って、水挿しをおこなうことができます。水挿しとは、剪定した枝を水に入れて発根させ、新しい株を増やすことです。
水挿しの方法は、水が入った花瓶やコップに剪定した枝を入れ、毎日水を変えるだけです。簡単なので、試してみるとよいでしょう。
【2】挿し木
剪定した枝は、挿し木をおこなうこともできます。挿し木とは、水挿しとは違い、剪定した枝を土に挿し込んで増やすというやり方です。挿し木の手順を以下で簡単にご説明します。
【1.剪定した枝を処理】
剪定した枝は10cmほどに切り、節を1~2個残した状態にしておいてください。このとき、切り口が斜めになるように切ってください。そうすることで、切り口の面積が多くなるので、水分をたくさん吸収することができ、より確実に発芽させることができるのです。
葉は枝全体のうち2~3枚残してすべて取り除きます。また、吸水と蒸散のバランスを保つために、葉を3分の1程度切っておきましょう。
【2.切り口を水につける】
切り口を1~2時間程度水につけてください。この作業を水揚げといい、乾燥して枯れることを防ぐため、枝葉に十分な水分を補給するための作業です。
【3.土の準備】
鉢に軽石を入れ、その上に赤玉土を入れましょう。
【4.カポックの枝を土に挿す】
最後に、カポックの枝を土に挿し、水やりをおこなえば作業完了です。
【3】ハイドロカルチャー
ハイドロカルチャーとは、「ハイドロボール」という石に枝を挿して植物を育てる方法です。ハイドロボールとは、粘土からつくられたボール状の石のことです。
ハイドロボールは見た目がボール状でおしゃれなので、透明な容器に入れればインテリアとしても使うことができます。
また、ハイドロカルチャーを使えば、虫が寄ってくることはほとんどなくなります。そのため、「室内で育てたいけど虫が寄ってくるのが心配……」という方にもおすすめです。
ハイドロカルチャーでは、まず容器の底に根腐れ防止剤を敷いた後に、水洗いしたハイドロボールを敷き詰めてください。そこにカポックの枝を挿せば作業完了です。
【4】茎伏せ
茎伏せ(くきふせ)とは、茎を土の上に寝かせて増やす方法です。茎伏せでは、葉を取り除いた状態の茎を3~5cmほどに切り、約2か月間湿った土に寝かせれば、根を出すことができます。
ここまで、カポックの枝の活用方法をお伝えしてきました。上記のような方法で増やしたカポックも、形を整えたり、風通しや日当たりを改善したりするためにも、定期的に剪定をおこなわなければなりません。
もし、自分での剪定が難しければ、剪定業者に依頼するとよいでしょう。そうすることで、手間をかけず、カポックをキレイに剪定することが可能です。
弊社の加盟店では、実績のあるスタッフが在籍しています。もしカポックの剪定を自分でおこなうのが難しいときには、お気軽に弊社までお問い合わせください。
カポックに元気がない……原因と対処法
ここからは、カポックが弱ってしまう原因と対処法をお伝えしていきます。「カポックに元気がないかも……」と思う方は、以下の内容に当てはまっていないか確認してみてください。
【原因1】乾燥

カポックを乾燥させた状態で放置すると、弱ってしまうおそれがあります。とくに、室内で育てる場合にはエアコンの風が直接当たると乾燥してしまうことがあります。カポックにエアコンの風が直接当たらないような位置に置きましょう。
【原因2】日照不足
カポックは耐陰性が高いため、ある程度日が当たらなくても育てることができます。しかし、まったく日の当たらない場所だと、光合成をおこなうことができずに枯れてしまうおそれがあります。そのため、カポックを置く場所は、だいたい1日に数時間程度日光が当たるところがよいでしょう。
【原因3】根腐れ
根腐れとは、その名のとおり根が腐ることで、酸素を吸収できなくなることで起こります。根腐れが起こると、植物が弱ってしまいます。
根腐れは、水のやりすぎによって起こります。根腐れを防ぐには、土が乾いてからおこなうようにしてください。
「あれ、まさか枯れた?」と思ったら……
カポックに元気がないとき、「乾燥」「日照不足」「根腐れ」が起こっていないか確認してみてください。しかし、それでも原因がわからないときには、それ以外の原因が考えられるので、一度剪定業者に相談してみることをおすすめします。
剪定のプロである業者に相談することで、カポックに元気がない原因を特定できる可能性が高いです。
弊社では、カポックの剪定をおこなう業者をご紹介します。24時間365日電話受付しているので、ご都合のよい時間帯にいつでもお電話いただくことができます。カポックの剪定にお悩みの方は、ぜひ弊社までご連絡ください。
剪定の関連記事
- 大王松(ダイオウショウ)の剪定方法|剪定道具や注意点・育て方も
- クロガネモチ剪定|適期と目的「樹高の調節・枝の除去」で違う方法
- びわの剪定に適した時期・剪定方法とは?収穫アップに役立つ情報も!
- 甘くて大きい実のために!ブルーベリー剪定のコツと注意点
- 松剪定失敗で枯れることもある!?原因や症状・正しい方法・時期
- ハコネウツギの剪定|開花させるなら時期が重要!正しい手入れも解説
- パキラ剪定の時期と方法を紹介!パキラは挿し木で増やすこともできる
- ナナカマドの剪定は1月頃の落葉期に!初心者もできる上手な育て方
- ラベンダーのお手入れ方法をご紹介!育てかた・剪定・増やしかた
- スモークツリーに剪定はかかせない!育てかた・増やしかたもご紹介!