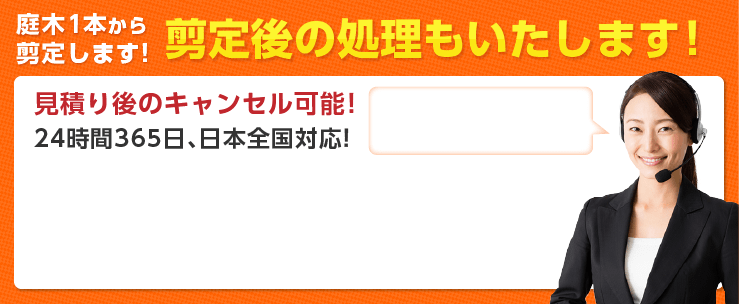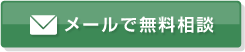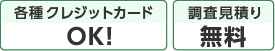もみの木剪定のキホン!美しい形に仕立てよう|お手入れ方法も解説

もみの木は40メートルを超える高木の仲間なので、放っておくと手に負えないほどの高さに成長してしまいます。そのため、「手に負えなくなるほど大きくなっても困るから、高さをおさえたい……」「伸びた枝葉が近所の迷惑になると困るから、枝葉を短くしたい……」という思いから、剪定を考えている人もいらっしゃることでしょう。
そこで、今回はもみの木の剪定方法についてご紹介します。もみの木の剪定では、高さをおさえる「芯止め」という方法が大切です。また、もみの木を健康的に保つためのお手入れ方法についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
もみの木剪定のキホン
もみの木は剪定せずに放置しておくと、枝が伸び放題になって樹形が悪くなります。そのため、定期的に剪定をすることによって形を整えましょう。もみの木には基本的な剪定と、場合に応じておこなう強剪定があるため、その方法についてご説明します。
もみの木の剪定時期

もみの木の剪定は、おもに10~3月前後におこないます。植物は冬から春先にかけて、気温の低い環境で生き延びるために、エネルギー消費をおさえることで成長がおそくなるのです。そのため、剪定してもすぐに枝が伸びてくる心配がありません。
基本的な剪定
樹形を整えるための基本的な剪定では、長くなりすぎた枝を切り戻し、長さのバランスを整えます。また、内側に反り返った枝や枯れ枝など、樹形を乱す原因になる枝は、根元から切り落としましょう。中途半端に枝の一部を残していると、切り口の近くから再び枝が生えてくるためです。
強剪定
もみの木の枝数が多く、密生している場合は「強剪定(きょうせんてい)」も必要です。強剪定とは、多めに枝を切り落とすことで、風通しや日当たりを改善する方法をいいます。
もみの木は風通しの悪い環境を嫌うため、枝葉がたくさんあって空気がこもっていると、弱る原因になります。そのため、枝の数を減らすことによって、もみの木の健康を守ることができるでしょう。
剪定をするときは、根元から枝を切り落としてください。先述のとおり、枝の一部が残っていると、切り口からすぐに新しい枝が生えてきてしまうのです。
強剪定は難しい
強剪定では枝を多めに落とすため、もみの木へのダメージも大きくなります。もみの木は剪定のダメージに対して強くはないため、切り過ぎると枯れるおそれもあるのです。そのため、強剪定をおこなうなら業者に任せることをおすすめします。
剪定のノウハウを知り尽くした業者に任せることで、もみの木が枯れない加減で剪定をしてくれるでしょう。また、剪定の方法を教えてもらうことで、今後、自力で手入れをするための手本になるかもしれません。
業者への依頼をお考えなら、ぜひ弊社へご相談ください。弊社ではお客様のご希望にできるだけ近い業者をピックアップし、ご紹介させていただきます。弊社は無料で電話やメールでのご相談を受けつけていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
もみの木が大きくなりすぎてしまったら?
もみの木は成長が早く、放置しておくとみるみるうちに大きくなります。そのため、大きく育ちすぎないように、「芯止め」というもみの木の剪定をして高さをおさえることが大切なのです。そこで、以下ではもみの木の特徴を踏まえたうえで、芯止めの必要性と方法についてご説明します。
もみの木の特徴

もみの木は松の仲間で、細長い葉をもつ針葉樹です。きめ細かな葉と、真っすぐ三角形にそびえ立つ姿から、洋風の家にも日本家屋にも合う魅力があります。また、もみの木はクリスマスツリーの木としても使われることが多いため、冬の飾りつけを楽しむこともできるでしょう。
しかし、その樹高は大きいもので40メートルを超えることもあり、放っておくと手がつけられないほど大きく育ってしまいます。鉢植えの場合は大きくなりにくいですが、庭植をすると育ちすぎる危険があるため、芯止めをして高さをおさえましょう。芯止めの方法については、次でご説明します。
もみの木には「芯止め」が大切
芯止めとは、幹の頂上を切ることで、高さをおさえる方法です。植物の多くは、幹のほうが優先的に育つ性質があります。そのため、中心部である幹を短くすることで、栄養が枝のほうへ回るようになり、高くなりすぎることを防げるでしょう。
大きくなりすぎてしまったら
すでに大きくなったもみの木を芯止めする場合、高所での作業になります。そのため、自力でおこなうよりも、業者に任せてください。高所での作業では、転落事故のリスクをともなうためです。業者によっては、高所作業のための機材をもっている場合もあるため、自力でおこなうより安全に作業ができるでしょう。
弊社にご相談いただければ、高所作業にも対応した業者をご紹介させていただくこともできます。また、弊社では1本の木の剪定からでも受付をしていますので、相談したい点があればお気軽にご連絡ください。
もみの木を健康的に育てるお手入れのコツ
もみの木は剪定だけでなく、日常的なお手入れも大切です。もみの木は寒さに強いぶん、暑さや乾燥を苦手とするため、適切な方法でお手入れをする必要があります。そこで、以下ではもみの木のお手入れ方法についてご紹介します。正しいお手入れの方法を知り、育てる際にお役立てください。
育てる環境

もみの木を育てるときは、保水性の高い土に植えましょう。もみの木は乾燥に弱いため、水切れが続くと枯れることがあるのです。そのため、赤玉土やピートモスといった水持ちのいい土を用意しておきましょう。
土の選び方について自分では判断できない場合は、園芸用品店やホームセンターに足を運び、店員さんに「水持ちのいい土はどれか」と尋ねてみることをおすすめします。
また、もみの木を置く場所は、午前中だけ日が当たるような半日陰がよいです。もみの木は日光を好みますが、西日のような強い日差しに当たると、葉が傷んで枯れることもあるのです。そのため、半日陰の場所に植えるか、鉢植えにして午後は日陰に移動させましょう。
水やり・施肥
前述のとおり、もみの木は乾燥を嫌うため、小まめな水やりが必要です。毎日土の状態をチェックし、乾いていたら水を与えましょう。ただし、真昼に与えると、土中の水分が温まり、蒸れてしまうため、もみの木が弱る原因になります。そのため、気温が低い朝や夕方に水を与えるのがおすすめです。
また、もみの木を育てるには、定期的に施肥もおこないます。もみの木は3~5月にかけての春に、新しく芽を育てるためにエネルギーを使います。そのため、途中のエネルギーだけでは栄養不足になることがあるのです。
栄養を補助するために、3~5月にかけて有機肥料を与えましょう。有機肥料は効き目が長く続くため、栄養不足になるリスクが少ないのです。また、有機肥料は栄養が豊富なため、土中の養分がかたよる心配もありません。
有機肥料を使うときは、株まわりの土を掘り起こし、土と混ぜてまきましょう。有機肥料は土と混ざることで効果を発揮するのです。
注意すべき病害虫
もみの木は、基本的に病害虫には強いですが、剪定していないまま放っておくと、マイマイガがつくことがあります。マイマイガの幼虫である毛虫は、松の仲間である針葉樹に寄生しやすく、おもに葉を食害するのです。
マイマイガの幼虫は食欲旺盛なうえ、大量に発生するため、木の葉を食べつくされるケースもあります。そのため、発見したら殺虫剤をまいて駆除をしましょう。
ただし、マイマイガの幼虫にはかゆみをともなう毒針があり、殺虫剤を散布した際に針が飛散する危険があります。そのため、駆除する際はゴム手袋と長袖長ズボン、ゴーグル、マスクを着用し、長い箸やピンセット、トングなどで死骸を回収しましょう。
鉢植えは植え替えが大事
もみの木は鉢植えに植えることで、成長をおさえることができます。鉢植えのなかでは根を伸ばせる範囲が限られているため、一定の高さ以上は成長できないのです。
しかし、鉢のなかで根が密集すると、根詰まりといって木が弱る現象が起こるため、2年に1回の頻度で、大きな鉢に植え替えをしましょう。植え替えをするとき、根についている土を払いすぎてしなうと根にダメージが加わるため、軽く土を落とす程度にします。
もみの木はデリケートな面もある植物なので、うまく植え替えができるか不安な人もいるでしょう。また、もみの木が大きくなって、植え替えが難しいという人もいるかもしれません。
植え替えに不安があるときは、園芸関連の業者に相談してみましょう。剪定や植え替えなど、樹木に関する高い知識と技術と経験をもっている業者に作業をしてもらうことで、大切なもみの木を傷つけることなく植え替えができるのです。
業者を自力で探すのが大変なときは、弊社へご相談ください。弊社では、ご相談いただいたお客様に業者をご紹介させていただくため、ご自身で探すよりも迅速に「もみの木に関する悩みごと」を解決できるでしょう。弊社は年中無休でお電話を受けつけていますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
剪定の関連記事
- ツツジの剪定方法をチェック!剪定のタイミングは開花時期に合わせて
- シャリンバイ剪定は【花後】が肝心!お手入れして美しい花を楽しもう
- ブラシの木の剪定はタイミングが重要!増やしかた・育てかたも解説
- 剪定のコツがわかれば自分でできる!初めての庭作りは基本を押さえる
- ハスカップの剪定方法・育て方・増やし方│収穫量アップも夢じゃない
- レンギョウの剪定時期は12月から?剪定方法や育て方・植え方を解説
- イトヒバの剪定は定期的にやろう!適度な高さで健康的に育てる秘訣
- 柿の木を剪定方法を解説!タイミングと方法・収穫のための作業も
- ソヨゴの剪定時期は12月~2月!剪定方法と育てるポイントを解説
- 柏(カシワ)の木の剪定・お手入れについて|どんぐりから育てるには